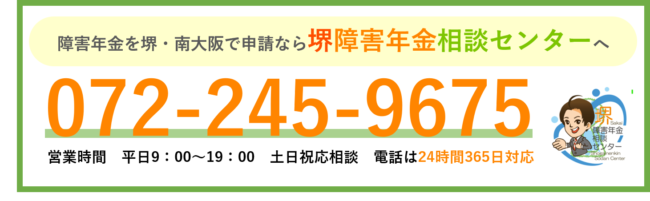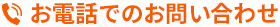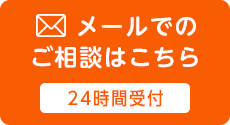人工関節(膝・股関節等)で障害年金はもらえる?専門家が永久認定などについて解説!
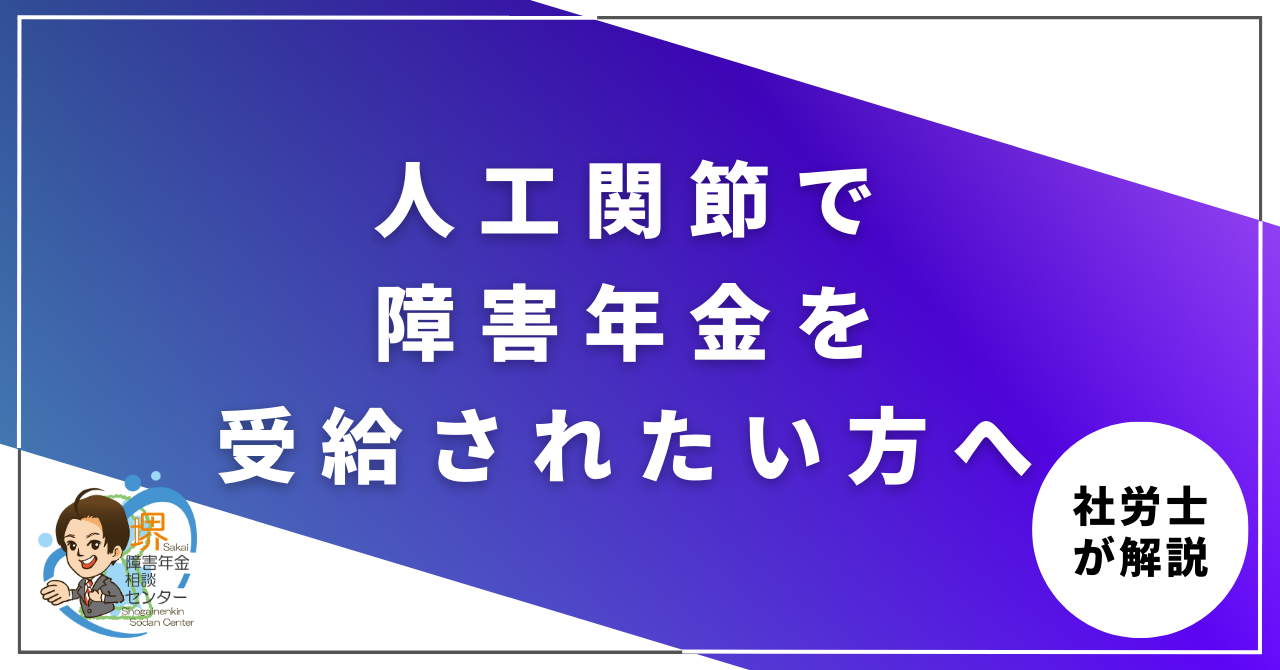
「障害基礎年金」とは、通常、20歳から64歳の方々を対象として支給される年金制度です。
この制度は、病気や事故の結果、障害を負った方々に支給されます。
具体的には、65歳未満で初めて病気や事故による診断を受けた方々で、日常生活や仕事に影響を与える障害を抱えている方々に支給されます。
今回は、人工関節を考えている方々に向けて、障害年金の申請に関する重要なポイントを説明いたします。
マンガで分かりやすく、人工関節で障害年金を受け取るポイントも解説しております!
Contents
人工関節で障害年金を受給する際のポイント
請求方法
障害年金は、時間が経過すると過去の期間分を受け取ることができなくなる場合もありますので、できるだけ早く請求する必要があります。
例えば、初診日から1年6ヶ月経過後に人工関節置換術を受けた方で、手術後1年以上経過してから障害年金の請求を行った場合、手術を行った月の翌月からの受給はできません。
この場合、事後重症請求となり、請求を行った月の翌月からしか受給できません。
もらえたはずの金額を逃さないためにも、早めの行動が必要です。
初診日について
障害年金を受給するためには、まずは初診日という重要な要件を満たす必要があります。
初診日とは、病気やケガにより初めて医師の診察を受けた日を指します。
この初診日に加入していた年金制度に応じて、障害基礎年金または障害厚生年金の種類が決定されます。
人工関節・人工骨頭の置換術を受けた方は、通常、障害等級3級に該当します。
ただし、受給するには初診日に厚生年金保険に加入していることが必要です。初診日に国民年金に加入していた方は、受給することはかなり難しくなります。
診断書について
肢体の障害用「様式120号の3」を使用します。
診断書⑬「人工骨頭・人工関節の装着の状態」に、部位および手術日を記入してもらいます。
通常は本来の障害認定日(初診日から1年6カ月)から1年を過ぎると診断書は2枚(障害認定日と現在)が必要になりますが、人工関節・人工骨頭の特例で認定日請求をする場合は現在の診断書1枚だけで構いません。
特例で受給できる可能性のある方

もうひとつ、ご注意いただきたい点があります。
初診日に国民年金に加入されていた方は、原則として認定されないことが多いですが、以下の条件を満たしていれば、認定される可能性があります。
①状態が悪化した場合
障害認定日では障害等級2級以上に該当せず受給できなかった場合でも、その後に症状が悪化して2級以上に該当すれば受給できる可能性があります。これを「事後重症請求」といいます。
事後重症請求の注意点として、年金は請求日の翌月分から支給されるため、請求が遅れるとその分、受け取れるはずの年金が消えてしまいます。そのため1か月でも早く請求する必要があります。
また、事後重症請求は、65歳の誕生日の前々日までに行う必要があり、老齢基礎年金の繰り上げをされた方はできません。
②社会的治癒が認められた場合
「社会的治癒」とは、初診日を「再発後の初診日」とすることをいいます。
一定期間(5年以上)受診せず、日常生活を問題なく過ごせていれば、いったん治癒したとみなし、再発日を新たな傷病の発病日とするという考え方です。
たとえば、幼少期に治療をしていて、体育の授業を問題なく受けていた、運動部で活動していた、肉体労働の仕事をしていたといった場合、日常生活に支障がなかったことを証明できれば、大人になってから再発した日を初診日として請求できます。
そうすることで初診日が厚生年金加入期間となれば、障害厚生年金3級を受給することができます。
社会的治癒は必ず認められるとは限りませんが、初診日が国民年金加入期間中や20歳より前の場合、初診日の証明が取れない場合などに、うまく活用できれば受給の可能性が高まります。
人工関節で障害年金はいくらもらえるの?

人工関節を置換している場合、原則3級となります。支給額は、報酬比例の年金額となります。
報酬比例部分の計算式を簡単に言いますと、「障害認定日の月までの給料の平均値に一定の乗率を掛けたもの×厚生年金加入月数(300月に満たなければ300)」です。
また、最低保証額というものがあり、障害厚生年金3級の場合、623,800円です。
人工関節挿入における障害認定基準
人工骨頭・人工関節をそう入置換された方は、以下の基準で障害認定されます。
一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換された方や、両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換された方は、3級と認定されます。
ただし、そう入置換してもなお「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級(2級以上)に認定されます。
※障害認定日の特例について
障害認定日は原則、「初診日から1年6か月後」となります。しかし人工関節・人工骨頭の場合は、「そう入置換した日」となります。これを「障害認定日の特例」といいます。
ただし、人工関節・人工骨頭をそう入置換した日が、初診日から1年6か月よりも後の場合は、原則の障害認定日で請求することになります。
人工関節の場合、永久認定になる?
障害年金の認定には、永久認定と有期認定の2つのタイプが存在します。
永久認定は、手足の切断や人工関節置換、失明など症状が変化しない場合に適用されます。
もし永久認定を受けると、終身で障害年金を受給することができます。
一方、有期認定は、症状が固定されない精神疾患や腎疾患、心疾患、がんなどほとんどの病気に適用されます。
時間の経過や治療により症状が軽くなることがあるため、有期認定の場合は定期的に更新手続きが必要です。
人工関節の場合の遡及請求について
人工関節を理由に障害年金を申請する際、「遡及請求」が可能なケースがあります。遡及請求とは、本来ならもっと早く障害年金を受給できていたにもかかわらず、何らかの理由で申請が遅れた場合に、過去に遡って年金を請求する手続きです。
人工関節と障害認定日
遡及請求が認められるためには、「障害認定日」という基準日を正しく把握することが大切です。人工関節の場合、手術を受けて関節が置換された日や、その後一定期間の経過をもって障害認定日とされることが多く、症状の重さや日常生活への支障の程度によって等級が判断されます。
特に、人工関節の手術を受けた直後から生活に支障があり、当時の診断書などでその状態が確認できる場合には、遡及請求の可能性が高くなります。逆に、手術後にある程度回復して就労や日常生活に大きな支障がない場合は、遡及請求が認められにくくなる傾向があります。
▶【2025年版】障害年金の遡及請求(遡り)とは?成功率や申請の注意点を社労士が解説!(クリック)
人工関節での障害年金受給事例
当事務所では、人工関節挿入により障害年金の受給が決定した事例が多数ございます。
是非ご自身のケースと照らし合わせみてください。
▶腰の痛み等で通院する中で股関節痛が出現したため、初診日の特定が難しかったが、人工股関節で障害厚生年金3級を受給できたケース(こちらをクリック)
▶約30年前の初診証明を取得できなかったが初診の年齢を特定し、障害厚生年金を受給できたケース【人工股関節で障害厚生年金3級】(こちらをクリック)
▶大腿骨頚部骨折(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース(こちらをクリック)
▶両変形性股関節症(人工股関節)で障害厚生年金3級に認められたケース(こちらをクリック)
専門家に障害年金申請サポートを依頼するメリット

専門家に依頼することで、障害年金の申請を効率的に進めることができるだけでなく、申請の成功率を高めることも可能です。
自分の権利をしっかりと守るために、専門家のサポートを活用することをおすすめします。
当事務所では、障害年金の申請手続きをスムーズに進めるために、経験豊富な社会保険労務士がサポートいたします。
当事務所は無料相談を行っております。是非お気軽にご相談ください。
まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。
お電話はこちらから
TEL : 072-245-9675(タップするとかかります)
営業時間:平日 9:00~19:00 土・日・祝日9:00〜16:00
※コールセンター受付時間:24時間
営業時間外に頂いたお電話はコールセンターでご用件のみ承り、翌営業日以降に折り返しご連絡する形での対応となります。
メールでのお問い合わせはコチラ

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。
- 2025.09.11コラムペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!
- 2025.07.15お知らせ【8/14 臨時休業のお知らせ】
- 2025.07.07コラム脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!
- 2025.05.30お知らせ【臨時休業のお知らせ】 誠に勝手ながら、社内研修のため 5月31日(土)は終日休業とさせていただきます。