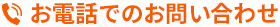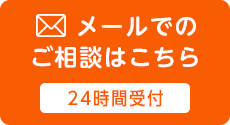脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!
脳梗塞を発症され、その後の後遺症と向き合いながら日々を過ごされている皆様、そしてそのご家族の皆様、誠に大変なこととお察しいたします。
手足の麻痺や言語障害、記憶力の低下など、目に見える症状から見えない症状まで、後遺症によって以前と同じような生活や仕事が困難になり、経済的な不安を抱えていらっしゃる方も少なくないでしょう。
そのような時に、皆様の生活を支える公的な制度として「障害年金」があることをご存知でしょうか。
この記事では、障害年金業務を専門とする社会保険労務士が、脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するための要件や認定基準、そして申請における重要なポイントを分かりやすく解説します。
「自分も障害年金をもらえる可能性があるのか知りたい」
「手続きが複雑そうで、何から手をつけていいか分からない」
そのようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ最後までお読みください。
Contents
障害年金とは?
障害年金とは、病気やケガによって日常生活や仕事に支障が出ている方に対して国から支給される公的な年金です。
「年金」というと高齢者が受け取る老齢年金のイメージが強いですが、障害年金は現役世代の方も受給できるのが大きな特徴です。
障害年金には、初診日に加入していた年金制度に応じて2つの種類があります。
|
種類 |
対象者 |
|
障害基礎年金 |
初診日に国民年金に加入していた方(自営業者、専業主婦(夫)、学生など) |
|
障害厚生年金 |
初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など) |
障害厚生年金の対象となる方は、障害の状態に応じて1級・2級に該当すれば障害基礎年金もあわせて受給できます。また、3級や障害手当金(一時金)という制度があるのも特徴です。
脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するための3つの要件
脳梗塞の後遺症で障害年金を受給するためには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1. 初診日要件
「初診日」とは、脳梗塞の症状(ろれつが回らない、手足の麻痺等)ではじめて医師または歯科医師の診療を受けた日のことを指します。この初診日がいつであるかによって、加入していた年金の特定や、後述する保険料の納付要件を満たしているかの判断が行われるため、非常に重要です。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料の納付済み期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。
ただし、この要件を満たせない場合でも特例があります。初診日が令和18年(2036年)3月31日までにある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たすことができます。
3. 障害状態要件
「障害認定日」に、国が定める障害等級に該当する程度の障害の状態にあることが必要です。障害認定日は、原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日です。
ただし、脳梗塞の場合、1年6ヶ月を待たずに症状が固定(肢体の障害のみ)した場合は、その症状が固定した日が障害認定日となり、1年6ヶ月より前に申請できることがあります。
脳梗塞の後遺症における障害認定基準のポイント
脳梗塞の後遺症は多岐にわたります。障害年金の認定においては、それらの後遺症が日常生活や労働にどの程度の支障を及ぼしているかが審査されます。
主な後遺症と認定基準のポイントは以下の通りです。
肢体の障害(片麻痺など)
身体の動かしにくさ(麻痺)に関する障害です。主に日常生活における動作がどの程度できるかで判断されます。
- 1級: 両手、両足の機能に著しい障害がある。日常生活が極めて困難で、常時介護を必要とする状態。
- 2級: 片方の手足、または両足の機能に著しい障害がある。食事や着替えなど、日常生活に多くの援助が必要な状態。
- 3級(厚生年金のみ): 片方の足の3大関節(股関節、膝関節、足関節)のうち2関節以上が動かせないなど、労働に著しい制限を受ける状態。
言語機能の障害(失語症)
言葉を理解したり、話したりすることが困難になる障害です。
- 2級: 日常会話が誰とも成立しない程度の障害。
- 3級(厚生年金のみ): 家庭内での簡単な会話はできるが、それ以上の会話が困難な程度の障害。
- 障害手当金(一時金):話すことや聞いて理解することのどちら か又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、 ある程度成り立つもの
高次脳機能障害(記憶障害・注意障害・遂行機能障害など)
記憶力や注意力、計画を立てて物事を実行する能力などに障害が現れるものです。外見からは分かりにくいため、その困難さを客観的に示すことが重要になります。
日常生活能力の7つの場面(食事、身辺の清潔保持、金銭管理など)について、「自発的にできるか」「援助が必要か」といった観点で評価されます。
複数の障害がある場合
上記の後遺症が複数残った場合、それぞれの障害の程度を総合的に評価して等級を決定する「併合認定」という仕組みがあります。例えば、肢体の障害が2級相当、言語機能の障害も2級相当の場合、併合して1級と認定される可能性があります。
脳梗塞での障害年金申請における注意点
脳梗塞の障害年金申請は、他の傷病に比べて特に注意すべき点が多くあります。
1. 診断書の重要性
医師が作成する診断書は、審査において最も重要な書類です。脳梗塞の後遺症は多岐にわたるため、ご自身の症状に合った診断書(肢体の障害用、精神の障害用など)を提出する必要があります。
また、医師に日常生活の不自由さを正確に伝えることが不可欠です。「これくらいは大丈夫だろう」と遠慮せず、具体的にどのような場面で、どれくらい困っているのかをメモにまとめて渡すなどの工夫が有効です。
2. 「病歴・就労状況等申立書」の作成
これは、ご本人やご家族が作成する書類で、発症から現在までの経過や、日常生活・就労における支障を具体的に申告するものです。
診断書だけでは伝わりきらない「生活のリアルさ」を伝える重要な書類です。特に高次脳機能障害など、外見から分かりにくい症状については、この申立書の内容が審査結果を大きく左右することもあります。
3. 初診日の証明
脳梗塞の初診は救急搬送されるケースも多く、どの病院が初診だったか曖昧になりがちです。また、時間が経ちすぎてカルテが破棄されていることもあります。初診日を証明する「受診状況等証明書」が取得できない場合でも、諦めずに他の資料で証明できる可能性がありますので、専門家にご相談ください。
社労士に依頼するメリット
障害年金の申請はご自身でも可能ですが、非常に複雑で時間も労力もかかります。専門家である社会保険労務士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 煩雑な手続きをすべて任せられる: 書類収集や作成、年金事務所とのやり取りなど、面倒な手続きを代行し、治療やリハビリに専念いただけます。
- 受給の可能性を高めるサポート: 専門家の視点で、認定基準を満たす的確な書類を作成します。特に「病歴・就労状況等申立書」は、ご本人の状況を審査側に正しく伝え、適正な認定に繋げるための重要な書類であり、私たちの経験とノウハウが最も活かされる部分です。
- 精神的な安心感: 「この書類で大丈夫だろうか」「不支給になったらどうしよう」といった不安から解放され、安心して結果を待つことができます。
当事務所における受給事例
脳梗塞(脳底動脈閉塞)で障害厚生年金3級が決定し、3年遡及も認められたケース
脳梗塞で障害厚生年金2級から障害厚生年金1級へ額改定請求できたケース
脳梗塞で障害基礎年金2級と認められ遡及額として約160万円を受給できたケース
まとめ
脳梗塞の後遺症と向き合いながらの生活は、ご本人様、ご家族様にとって大変なご苦労があるかと存じます。障害年金は、そうした方々の経済的な負担を軽減し、今後の生活を支えるための、国に認められた権利です。
「手続きが複雑そう」「自分は対象にならないかもしれない」と、最初から諦めてしまう必要はありません。適切な準備をして申請すれば、受給できる可能性は十分にあります。
もし、少しでも障害年金の受給をお考えでしたら、まずは一度、専門家である私たちにご相談ください。お一人おひとりの状況を丁寧にお伺いし、最適な方法をご提案させていただきます。一人で悩まず、私たちと一緒に、次の一歩を踏み出しましょう。
まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。
お電話はこちらから
TEL : 072-245-9675(タップするとかかります)
営業時間:平日 9:00~19:00 土・日・祝日9:00〜16:00
※コールセンター受付時間:24時間
営業時間外に頂いたお電話はコールセンターでご用件のみ承り、翌営業日以降に折り返しご連絡する形での対応となります。
メールでのお問い合わせはコチラ

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。
- 2025.09.11コラムペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!
- 2025.07.15お知らせ【8/14 臨時休業のお知らせ】
- 2025.07.07コラム脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!
- 2025.05.30お知らせ【臨時休業のお知らせ】 誠に勝手ながら、社内研修のため 5月31日(土)は終日休業とさせていただきます。
コラムの関連記事はこちら
新着情報の関連記事はこちら
- ペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!
- 【最新動向】障害年金の不支給が増加|精神・発達障害では2倍に
- 高額療養費制度の改正見送りについて
- ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請するポイントや注意点を社労士が解説
- GW期間中の営業日について
- 就労移行支援事業所で障害年金の勉強会を開催いたしました!
- 10月19日(木)国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)にて相談会を開催いたします。
- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!➂
- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!②
- 5月19日(木)にプルデンシャル生命保険株式会社にて勉強会を実施いたしました
- 2021.2 .22発行 ぎょうけい新聞社「士業プロフェッショナル」に掲載されました
- 令和3年3月分から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
- TVホスピタル2019年3月号vol.56の紙面に相談会告知しました
- 12月6日(木)貝塚市民福祉センターで無料相談会を開催します
- お客様の声 2017年9月
- お客様の声 2017年8月
- お客様の声 2017年7月
- 障害年金の種類
- お客様の声 2017年6月
- お客様の声 2017年5月
- 堺で障害年金の認知活動を行っています
- お客様の声 2017年4月
- お客様の声 2017年3月
- お客様の声 2017年2月
- 9月4日に産経新聞に掲載されました!
- 10月1日より、事務所移転のお知らせ
- 平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。
- 【完全予約制】無料相談会開催@ビッグ・アイ(4~5月)