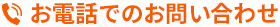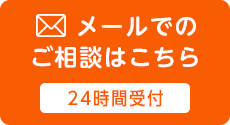ペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!
心臓の働きをサポートしてくれるペースメーカー。装着手術を乗り越え、少し安心されたことと思います。
しかし同時に、「以前のように仕事ができるだろうか」「日常生活での制限や、将来の経済的なこと」など、
新たな不安を感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
「ペースメーカーを入れたら、障害年金がもらえると聞いたけど本当?」
「自分も対象になるのだろうか?」
そんな疑問や不安を抱えるあなたのために、この記事では障害年金の専門家である社会保険労務士が、
ペースメーカーを装着された方の障害年金申請について、どこよりも分かりやすく解説します。
この記事を最後までお読みいただければ、障害年金を受給するための具体的な要件や、
申請における重要なポイント、そして多くの人が疑問に思う点まで、すべてご理解いただけます。
一人で抱え込まず、まずは正しい知識を得ることから始めましょう。
Contents
障害年金とは?
障害年金と聞くと、何か特別な制度のように思われるかもしれませんが、これは日本に住むすべての方が関わる公的な年金制度の一つです。
病気やけがによって、日常生活や仕事に支障が出てしまった場合に、現役世代の方でも受け取ることができる、経済的な支えとなる制度です。
障害年金には、初診日(ペースメーカー装着の原因となった病気で初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって、以下の2種類に分けられます。
- 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた方(自営業、専業主婦(夫)、学生など)が対象
- 障害厚生年金:初診日に厚生年金に加入していた方(会社員、公務員など)が対象
ご自身がどちらに該当するかで、受給できる年金の種類や等級が変わってきますので、非常に重要なポイントです。
ペースメーカーで障害年金を受給するための3つの基本要件
障害年金は、申請すれば誰でも受給できるわけではありません。以下の3つの基本要件をすべて満たす必要があります。
初診日要件
ペースメーカーを装着する原因となった傷病(例:不整脈、心筋梗塞、心不全など)で、初めて医師の診療を受けた日(=初診日)が明確であることです。この初診日によって、加入していた年金制度(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。
保険料納付要件
初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、
3分の2以上の期間で保険料を納めているか、または免除されている必要があります。
(特例として、初診日が令和8年3月31日までにある場合は、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければ良いとされています。)
「未納が多くてダメかも…」とご自身で判断せず、まずは年金事務所や専門家にご確認ください。
障害状態要件
障害の程度が、国が定めた障害等級に該当している必要があります。
ペースメーカーを装着した場合、この障害状態の判断に明確な基準が設けられています。
次の章で詳しく見ていきましょう。
ペースメーカー装着者の障害認定基準:「原則3級」の真実と注意点
ペースメーカーを装着された方の障害等級は、
日本年金機構の「障害認定基準」において、明確な指針が示されています。
・「ペースメーカーを装着したものについては、原則として、障害の程度を3級と認定する。」
そのほか、以下の障害等級となります。
【3級】
・ペースメーカー(原則)
・人工弁(原則)
【2級】
・CRT(心臓再同期医療機器)
・CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)
【1級】
・心臓移植
・人工心臓
ここから分かる重要なポイントと、注意点を解説します。
障害厚生年金なら「原則3級」
この基準の通り、初診日に厚生年金に加入していた方がペースメーカーを装着した場合、
原則として障害厚生年金3級に認定されます。
日常生活やお仕事に大きな支障がないように見えても、
体にペースメーカーという異物を入れていること自体が、障害として認められるということです。
初診日が国民年金(障害基礎年金)の場合は要注意
最も注意が必要な点です。
障害基礎年金には、1級と2級しかなく、3級という等級が存在しません。
そのため、初診日に国民年金に加入していた方がペースメーカーを装着し、
「原則3級」に該当すると判断された場合、障害基礎年金は受給できないということになります。
このことを知らずに申請準備を進めてしまい、
不支給となってからご相談に来られるケースは少なくありません。
また、先天性の心臓疾患がある場合、
20歳前に医療機関を受診していれば、障害基礎年金での請求対象となります。
ただし、次のようなケースがあります。
- 未成年の時に心臓手術を受けた
- その後、症状が落ち着き、通常の生活を送っていた
- 成人後になって再び心臓に関する症状が現れた
この場合、医学的に見ると手術の時点で「完全に治った」とは言えないこともあります。
しかし、障害年金の制度上は、症状がなく通常の生活を長期間送れていた状態を「社会治癒した」とみなし、
いったん完治したものと取り扱うことがあります。
その結果、成人後に症状が再び現れ、改めて医療機関を受診した日に厚生年金に加入していた場合、
障害厚生年金で請求できる場合があります。このあたりは実務上かなり難しくなりますので、専門家にご相談ください。
2級以上に該当するケースも
「原則3級」とされていますが、あくまで原則です。
ペースメーカーを装着してもなお、心機能の低下が著しく、
日常生活に大きな支障が出ている場合は、2級や1級に認定される可能性もあります。
例えば、「少し動くだけで息切れや動悸がする」「介助がなければ身の回りのことができない」といった状態であれば、
より上位の等級に認定されることも視野に入れて申請を検討すべきです。
ペースメーカーの障害年金申請で最も重要な2つのポイント
「原則3級」という基準があるからといって、申請が簡単というわけではありません。以下の2つの書類の内容が、審査の結果を大きく左右します。
ポイント1:医師に提出する「診断書」
診断書は、障害年金を申請する上で最も重要な書類です。ペースメーカーの場合、「循環器疾患用の診断書」を使用します。 医師に現在の状態を正確に診断書へ反映してもらうために、以下の点を意識しましょう。
自覚症状を具体的に伝える:
ペースメーカー装着後も残っている症状(動悸、息切れ、めまい、疲れやすさなど)を、どんな時に、
どのくらいの頻度で起こるか、具体的に伝えましょう。
「日常生活で不便に感じること」をメモにまとめて渡すのが効果的です。
「一般状態区分表」と「日常生活活動能力及び労働能力」の記載:
診断書には、日常生活や労働能力を評価する項目があります。
ここが実態よりも軽く記載されてしまうと、不支給のリスクが高まります。
ご自身の状態を客観的に、そして正確に医師に伝える努力が重要です。
ポイント2:自分で作成する「病歴・就労状況等申立書」
これは、発症してから現在までの経緯をご自身の言葉で伝える唯一の書類です。
診断書だけでは伝わらない、日常生活の困難さを具体的にアピールするチャンスです。
時系列で矛盾なく:
発症から初診日、ペースメーカー装着手術、そして現在までの流れを、日付などを正確に、矛盾なく記載します。
装着前と装着後の変化を明確に:
ペースメーカーによって改善した点だけでなく、装着後も残っている症状や制限を具体的に書きましょう。
「〇〇はできるようになったが、△△は以前のようにできなくなった」
「長時間の立ち仕事は困難になった」
など、仕事や生活上の支障を具体的に記述することが、審査官に実態を伝える鍵となります。
もし障害年金が受給できたら?(当事務所の受給事例)
ここで、当事務所でサポートさせていただいた方の受給事例を一つご紹介します。
相談者
50代男性・会社員
傷病名
完全房室ブロックによるペースメーカー植え込み
状況
会社の健康診断で不整脈を指摘され、精密検査の結果、完全房室ブロックと診断。
ペースメーカーの植え込み手術を受けました。
術後は体調も安定し、元の職場に復帰できましたが、
長時間の残業や出張は制限されるようになり、収入が減少。
将来への経済的な不安から、当事務所にご相談されました。
結果
初診日が会社員時代であったため、障害厚生年金3級を受給。
年間約60万円の年金が支給されることになりました。
経済的な安心感が得られたことで、無理なく仕事を続けることができ、
治療にも前向きに取り組めるようになったと喜んでいらっしゃいます。
当事務所におけるその他の受給事例
心室頻拍、特発性拡張型心筋症(ICD)で障害厚生年金3級を受給できたケース
大動脈弁狭窄兼閉鎖不全症で障害厚生年金3級に認められたケース
専門家である社会保険労務士に相談する4つのメリット
ここまでお読みいただき、「自分一人で手続きするのは難しそうだ…」と感じられた方もいらっしゃるかもしれません。
障害年金の申請は非常に複雑で、専門的な知識が求められます。
社会保険労務士にご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
複雑な手続きの手間と時間を大幅に削減できる
必要書類の取り寄せから作成、年金事務所への提出まで、面倒な手続きをすべて代行します。
あなたは治療や体調の回復に専念できます。
受給の可能性を高めるための専門的なアドバイスがもらえる
あなたの状況を丁寧にヒアリングし、認定基準に即した的確な書類を作成します。
どうすればご自身の状態が正しく伝わるか、専門家の視点でアドバイスし、受給の可能性を最大限に高めます。
医師とのやり取りや書類作成の精神的ストレスから解放される
「医師にどうやって診断書の作成をお願いすればいいか分からない」「申立書の書き方が分からない」といった、
申請にまつわる精神的な負担を大きく軽減できます。
不支給決定後の不服申し立てもサポート
万が一、不支給という結果になっても、その決定に不服がある場合の審査請求・再審査請求といった手続きまで、
責任を持ってサポートします。
よくあるご質問
ペースメーカーの障害年金に関して、特によくいただく質問にお答えします。
Q1. ペースメーカーを装着すれば、誰でも障害年金3級がもらえますか?
A1. いいえ、誰でも受給できるわけではありません。
本文で解説した通り、「初診日要件」と「保険料納付要件」を満たしていることが大前提です。
特に、初診日に国民年金に加入していた方は、原則3級に該当しても障害基礎年金が受給できないため、注意が必要です。
Q2. 仕事を続けながらでも、障害年金は受給できますか?
A2. はい、受給できる可能性は十分にあります。
ペースメーカーを装着された方は、仕事に復帰されているケースも多くあります。
障害年金は、仕事をしているかどうかだけで判断されるものではありません。
仕事の内容に制限(残業ができない、重いものを持てない等)があったり、周囲の配慮があったりする場合、
その状況を「病歴・就労状況等申立書」で具体的に説明することで、受給に繋がるケースは多くあります。
Q3. 障害年金の更新は必要ですか?永久認定ではないのですか?
A3.ペースメーカーを装着している場合でも、必ずしも「永久認定」になるわけではありません。
心疾患は、その後の経過によって症状や状態が変化する可能性があります。
そのため、障害年金の認定では、
「有期認定」(一定期間ごとに見直しを行う認定1年から5年)がされるケースが多く見られます。
Q4. ペースメーカーの電池交換をしたら、何か手続きは必要ですか?
A4. 電池交換の手術自体で、新たに障害年金の申請手続きが必要になることはありません。
ただし、もし有期認定で更新が必要な場合は、
その際の診断書に電池交換を行った事実を記載してもらうことになります。
電池交換によって体調が大きく変化した場合は、
等級の見直しを求める「額改定請求」ができる可能性もあります。
まとめ:諦める前に、専門家へご相談ください
この記事では、ペースメーカーを装着された方の障害年金について、
認定基準や申請のポイントを詳しく解説しました。
- ペースメーカーを装着した場合、初診日に厚生年金に加入していれば、原則として障害厚生年金3級に認定される。
- ただし、初診日に国民年金加入だと、3級がないため原則受給できない。
- 「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の内容が審査を大きく左右する。
- 申請には専門的な知識が必要で、一人で抱え込むのは禁物。
ペースメーカーを装着し、これからの生活に不安を抱えているのは、あなただけではありません。
障害年金は、そんなあなたの生活を支えるためにある、正当な権利です。
「自分の場合はどうだろう?」
「要件を満たしているか分からない」
そう思われたなら、どうか諦める前に一度、私たち障害年金の専門家にご相談ください。
あなたの状況を丁寧にお伺いし、受給の可能性があるか、どのような準備が必要か、親身になってアドバイスさせていただきます。
まずはお電話かメールで無料相談のご予約をしてください。
お電話はこちらから
TEL : 072-245-9675(タップするとかかります)
営業時間:平日 9:00~19:00 土・日・祝日9:00〜16:00
※コールセンター受付時間:24時間
営業時間外に頂いたお電話はコールセンターでご用件のみ承り、翌営業日以降に折り返しご連絡する形での対応となります。
メールでのお問い合わせはコチラ

- 社会保険労務士
-
ご覧いただきありがとうございます。
堺・南大阪を中心に大阪府全域の障害年金申請をサポートしております。
障害年金について不安を感じたり、わからないことがあったりしたときは、
ぜひ当事務所にお気軽にご相談下さい。無料でお話を聞かせて頂きます。
- 2025.09.11コラムペースメーカーで障害年金はもらえる?原則3級の認定基準と申請の全ポイントを社労士が徹底解説!
- 2025.07.15お知らせ【8/14 臨時休業のお知らせ】
- 2025.07.07コラム脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!
- 2025.05.30お知らせ【臨時休業のお知らせ】 誠に勝手ながら、社内研修のため 5月31日(土)は終日休業とさせていただきます。
コラムの関連記事はこちら
新着情報の関連記事はこちら
- 脳梗塞の後遺症で障害年金はもらえる?認定基準や申請のポイント社労士が解説!
- 【最新動向】障害年金の不支給が増加|精神・発達障害では2倍に
- 高額療養費制度の改正見送りについて
- ADHD(注意欠如・多動性障害)で障害年金を申請するポイントや注意点を社労士が解説
- GW期間中の営業日について
- 就労移行支援事業所で障害年金の勉強会を開催いたしました!
- 10月19日(木)国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)にて相談会を開催いたします。
- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!➂
- 産経新聞社「暮らしのミカタ~社会保険労務士相談室~」に阪本のインタビューが掲載されました!②
- 5月19日(木)にプルデンシャル生命保険株式会社にて勉強会を実施いたしました
- 2021.2 .22発行 ぎょうけい新聞社「士業プロフェッショナル」に掲載されました
- 令和3年3月分から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
- TVホスピタル2019年3月号vol.56の紙面に相談会告知しました
- 12月6日(木)貝塚市民福祉センターで無料相談会を開催します
- お客様の声 2017年9月
- お客様の声 2017年8月
- お客様の声 2017年7月
- 障害年金の種類
- お客様の声 2017年6月
- お客様の声 2017年5月
- 堺で障害年金の認知活動を行っています
- お客様の声 2017年4月
- お客様の声 2017年3月
- お客様の声 2017年2月
- 9月4日に産経新聞に掲載されました!
- 10月1日より、事務所移転のお知らせ
- 平成28年6月1日より代謝疾患(糖尿病)による障害の障害認定基準が改正されます。
- 【完全予約制】無料相談会開催@ビッグ・アイ(4~5月)